最判令和6年4月26日労経速2552号7頁(職種限定雇用契約と配転命令権)
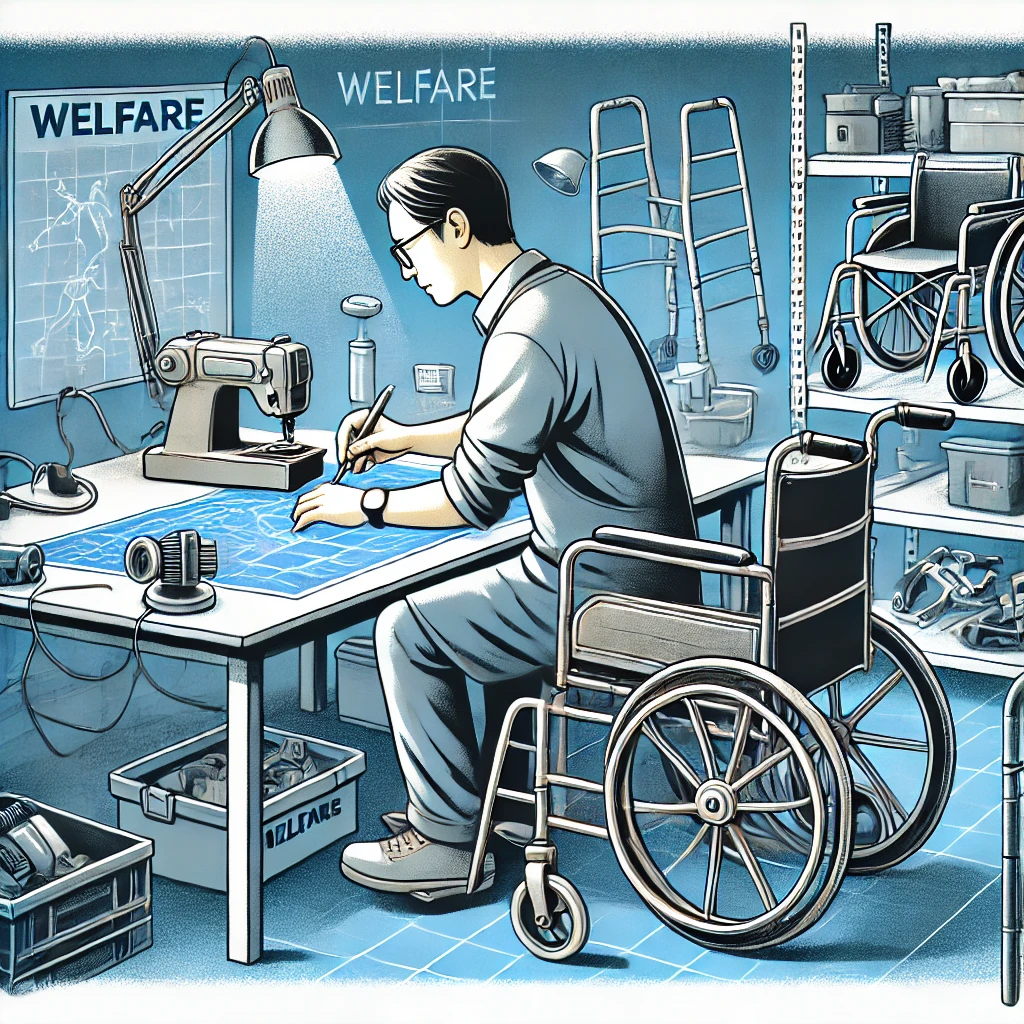
事案の概要
本件は、公的機関の指定管理者として福祉用具の製作・開発等を行う財団法人Yに雇用されていたXが、XY間には技術職に職種を限定する旨の合意があるにも関わらず、総務課施設管理担当への配置転換を命じたことは違法であるとして、Yに対して損害賠償の請求などを行った事案である。原審は、Yの配置転換命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないとしてXの請求を棄却したため、Xが上告した。
判旨
「原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1) 公の施設であるA社会福祉センターの一部であるA1福祉用具センター(以下、単に「福祉用具センター」という。)においては、福祉用具について、その展示及び普及、利用者からの相談に基づく改造及び製作並びに技術の開発等の業務を行うものとされており、福祉用具センターが開設されてから平成15年3月までは財団法人B財団が、同年4月以降は上記財団法人の権利義務を承継した被上告人が、指定管理者等として上記業務を行っていた。
(2) 上告人は、平成13年3月、上記財団法人に、福祉用具センターにおける上記の改造及び製作並びに技術の開発(以下、併せて「本件業務」という。)に係る技術職として雇用されて以降、上記技術職として勤務していた。上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を上記技術職に限定する旨の合意(以下「本件合意」という。)があった。
(3) 被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付けでの総務課施設管理担当への配置転換を命じた(以下、この命令を「本件配転命令」という。)。
3 原審は、上記事実関係等の下において、本件配転命令は配置転換命令権の濫用に当たらず、違法であるとはいえないと判断し、本件損害賠償請求を棄却すべきものとした。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該同意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。
そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば、この点に関する論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決中、不服申立ての範囲である本判決主文第1項記載の部分(本件損害賠償請求に係る部分)は破棄を免れない。そして、本件配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や、被上告人が上告人の配置転換に関し上告人に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」
解説
労働者と使用者の個別契約において、勤務場所や職種を特定の範囲に限定ないし特定する合意がなされた場合、その範囲を超えて配置転換を命じることは出来ないと考えられており、就業規則の一般的は移転条項によってその変更を命ずることも出来ないと解されている(荒木尚志「労働法」 第4版 455頁ほか通説)。
もっとも、医師や自動車運転手などのように、特別の技能や資格を有する場合はともかく、そうでない場合には、職種を限定する合意自体が成立したとは認められないとして、配置転換命令を違法でないとする裁判例が一定数見られるところである(日産自動車村山工場事件 最判平成元年12月7日労判544号6頁)。
本件においては、判旨では「上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を上記技術職に限定する旨の合意(以下「本件合意」という。)があった。」としか述べられておらず、どのような事実関係に立脚してかかる合意が成立していたと認定されたのかは判然としない(ウエストローには、原審の詳細までは掲載されていなかった)。とはいえ、そのような合意が存在しているのであれば、配置転換命令が配置転換命令権の濫用に該当するか否かを判断する以前の問題として、配置転換命令権自体が存在しないことになるのであり、判旨は極めて正当である。原審の単純ミスというほかない。
これまでの裁判例が、職種限定の合意を認めることに慎重であった背景には、①使用者(企業)側の事情として、年功序列、終身雇用を前提とした雇用システムを維持するためには、配転による柔軟な労働条件変更を認めざるを得ないという、かつてのメンバーシップ型雇用を前提とした実質的考慮に加え、②労働者にとっても、職種限定の合意が認められてしまうと、当該職種に関して業務不適格とされた場合に、他の職種への異動により雇用を維持することなく解雇することの適法性がより認められやすいため、労働者の地位の安定性という観点からは必ずしも有利とは言えないという考慮も働いていたのではないかと思われるところである。そのような考え方の派生として、配転命令権の存在自体は柔軟に認めつつ、特定についての労働者の期待等を考慮し、配慮に欠ける配転を配転権の濫用として処理する考え方が、裁判例では多数になってきていたとの指摘がある(前掲荒木457頁。東亜ペイント事件最判昭和61年7月14日労判477号6頁)。
しかしながら、日産自動車村山工場事件にしても東亜ペイント事件にしても、バブル期の、新卒一括採用から終身雇用を前提にゼネラリストを養成するという、メンバーシップ型雇用が(少なくとも大企業においては)当然のごとくに考えられていた時代の判例であることには留意しなければならない。
現代では、労働者の特定の資格や技能に着目したジョブ型雇用が、大企業では優勢になりつつあり、またワークライフバランスの観点や労働者の価値観の変化などから、転勤を忌避して特定の地域における勤務を希望する労働者が増加しつつある。労働契約の内容として、職種や勤務地等を特定の範囲に限定する雇用契約は、そうした現代的な労働者の価値観や労働環境に合致するものとして捉え直す必要があるのではなかろうか。そこに、高度経済成長期の「亡霊」とも言うべき、メンバーシップ型雇用を前提とする判断枠組みを当てはめることは、時代錯誤との謗りを免れないと思われる。原審は、そうした落とし穴にはまってしまったのではないだろうか。
本判決は、それ自体を取り出して考えると、従前から通説とされている考え方に立脚するもので、特に目新しい論点を提供するものではない。しかしながら、ジョブ型雇用を前提とする雇用契約に、安易にメンバーシップ型雇用の発想を当てはめて配置転換命令を行うことのリスクについて今一度注意喚起する事例であると言え、雇用主としては改めて注意する必要があろう(本事案に関して言えば、そもそも、XがわざわざYに対して損害賠償を請求して最高裁まで係争しているという時点で、報復人事など、配転命令がよほどXの腹に据えかねる内容だったのではないかと推測されるところである)。
リンク
